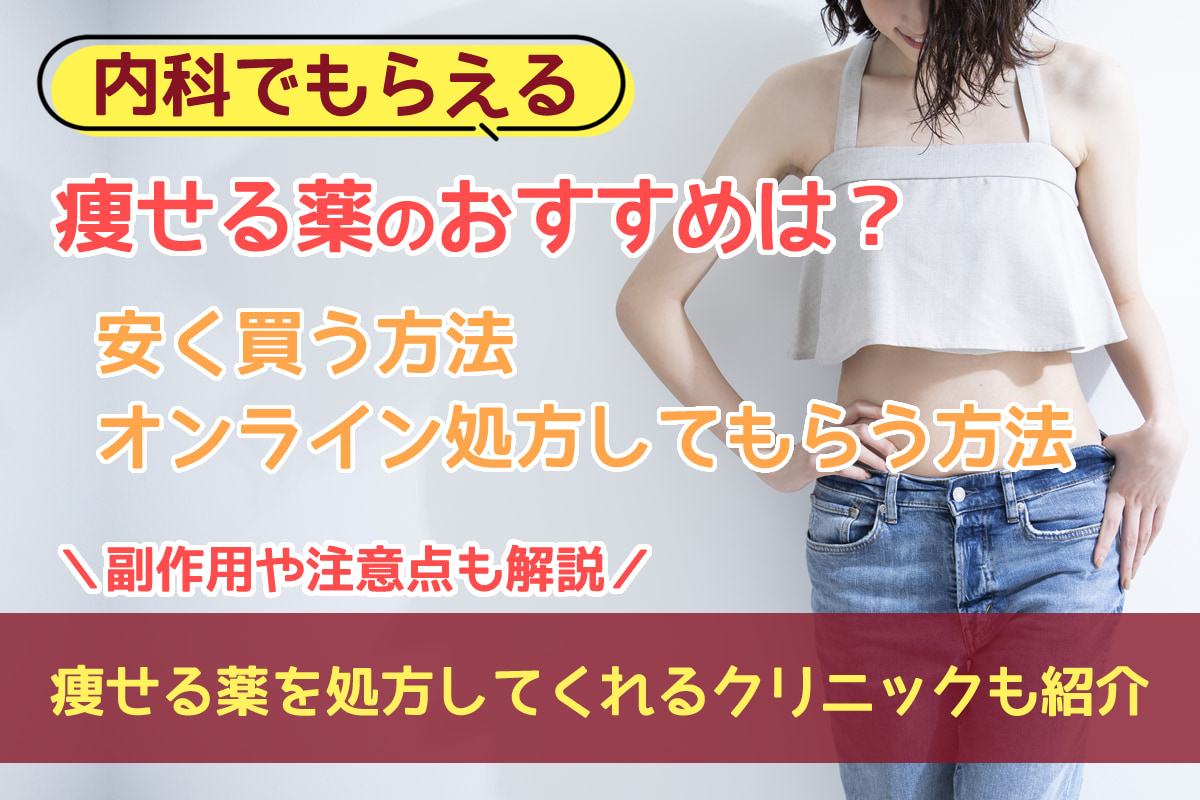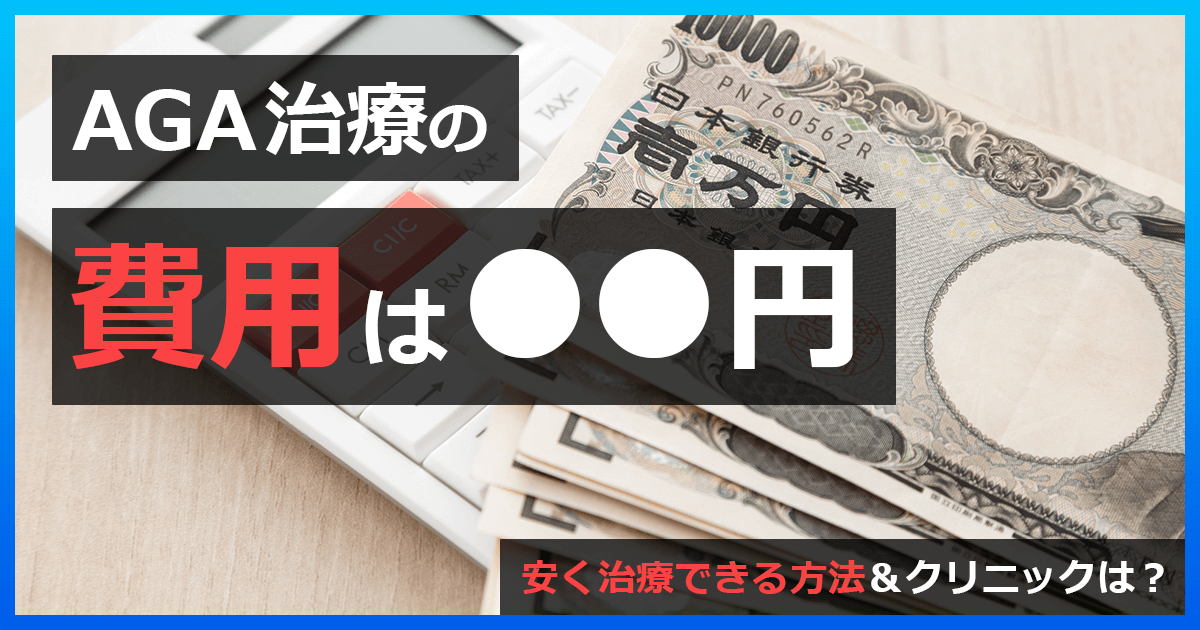ダイエットをしたいと思った時に「食事はどうすればいいのか?」と悩む方も多いでしょう。
食事とダイエットには大きな関りがあり、毎日の食事内容や食事方法を改善するだけでもダイエットをすることが可能です。
ここでは、ダイエット中の食事のルールやおすすめの痩せる食べ物、ダイエットを成功させるための痩せる食事方法なども解説しますのでぜひダイエットの食事の参考にしてください。
ダイエット中の食事ルールは2つ!痩せる食事の基礎知識
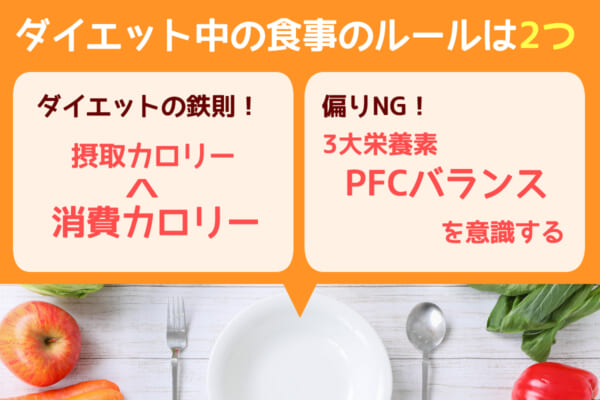
ダイエット中に気を付ける食事のルールは大きく分けて2つです。
ポイントは、
- カロリーを摂り過ぎないこと
- バランスの良い食事をすること
カロリーの制限はもちろん必要ですが、ただカロリーを減らせばいいわけではありません。
健康な体を維持するためには、食事内容や栄養バランスにも気を配ることが大切です。
ダイエットのコツは、食事から摂取したカロリーをしっかり消費しつつ、健康維持に必要な栄養素を上手に取り入れることにあります。
食事以外に5つの痩せる方法もまとめていますのでご一緒にご覧ください。
1)ダイエットの鉄則!摂取カロリー<消費カロリーにする
多少の個人差はありますが、
体脂肪を1kg落すために必要な消費カロリーは7,200kcal
だと言われています。
このカロリーを消費するためには、日々の摂取カロリーが消費カロリーを下回ることが鉄則です。
一般的なダイエットは、身体活動などで消費するエネルギーよりも、食事で摂取するエネルギーを少なくすることで体重を減らします。一日の基礎代謝量は、成人男性約1,500キロカロリー、成人女性で約1,150キロカロリーです。
引用元:厚生労働省 e-ヘルスネット|ダイエット
1日の消費カロリーは、「基礎代謝量×身体活動レベル」の式で求められます。
性別や年齢・体質によっても異なりますが、身体活動レベルがふつうの人の場合、
- 成人男性で約2,500〜2,700kcal
- 成人女性で約2,000〜2,200kcal
この数字よりも、摂取カロリーが上回ると使いきれなかったエネルギーが脂肪として蓄えられることになり、ダイエットは成功しません。
食生活の工夫や適度な運動などを組み合わせて、毎日200〜240kcalを減らすことができれば一か月で-1kgの減量が可能になります。
2)偏りNG!3大栄養素PFCバランスを意識する
カロリーを制限するために、偏った食生活をするとかえって健康を害することに繋がります。
カロリーの少ないものばかり食べたり極端に食事量を制限すると、亜鉛やリン、カリウム、カルシウム、鉄などのミネラルが不足してしまいます。
これらのミネラルは体内で作ることができないため、食事から必要量を摂取する必要があるのです。
ミネラルが不足すると、
- イライラするなど情緒が不安定になる
- 貧血や肌荒れ
- 免疫力の低下
なども起こりやすくなります。
また、食事から得ている栄養素の中で、エネルギーとして使用されるのは「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」の3つです。
この3大栄養素はそれぞれの英語の頭文字を取りPFCと呼ばれ、この3つのバランスを意識した食生活をすることでダイエットの成功だけでなく、生活習慣病の予防や改善にも役立ちます。
たんぱく質、脂質、炭⽔化物は、エネルギーを産⽣する栄養素です。肥満ややせを防ぐためにエネルギーを過不⾜なく摂取するとともに、⽣活習慣病予防の観点から、たんぱく質、脂質、炭⽔化物の摂取量をバランスよくとることが⼤切です。
引用元:消費者庁|たんぱく質、脂質、炭水化物をバランスよくとる
期間を決めて行うファスティングといった断食ダイエット方法もありますが、ファスティングのやり方は特殊なため食事の基本はPFCバランスを意識することが必要です。
P=Protein/たんぱく質は積極的に

たんぱく質は、筋肉を作るもとになる栄養素です。
筋肉が多いと、体内の基礎代謝が上がり、脂肪が燃えやすくカロリーを消費しやすい体になります。
そのため、筋肉量を落さないためにも適切な量のたんぱく質を摂取することはダイエットを継続する上でとても重要です。
たんぱく質の種類によりその代謝回転速度は異なるが、いずれも分解されてアミノ酸となり、その一部は不可避的に尿素などとして体外に失われる。したがって、成人においてもたんぱく質を食事から補給する必要がある。
引用元:日本人の食事摂取基準(2020 年版)
しかし、たんぱく質を摂るだけでは痩せることはできません。
適量のたんぱく質を摂取したあとは、筋トレや適度な運動を行い筋肉をつけ、基礎代謝を上げることが大切です。
たんぱく質は、筋肉のほか髪の毛や皮膚、血液、骨などの材料にもなるため、不足しないように積極的に取り入れることで肌や髪の質を守りながら美しく痩せられます。
たんぱく質は20種類ほどのアミノ酸からできていますが、その中で体内で合成できない9種類を必須アミノ酸と言います。
必須アミノ酸は動物性たんぱく質に多く含まれています。
それゆえに、動物性たんぱく質も植物性たんぱく質もバランスよく摂取するように心がけましょう。
たんぱく質は1gあたり4kcalのエネルギーを生産します。
体重1kgあたり1g〜1.5gのたんぱく質が必要となりますので、この必要量をしっかり計算して、カロリーオーバーにならないようにしましょう。
目安として、成人女性の場合は1日に必要なたんぱく質は約50g、男性の場合は60〜65gです。
F=Fat/脂質はダイエットの敵!?

脂質は、たんぱく質と炭水化物と合わせて3大栄養素に含まれている要因です。
体の中でエネルギー源となるほかに体温を保つ役割の細胞膜や、ホルモンなどのもとになります。
脂質が不足すると、
- 低体温
- 肌荒れ
- 便秘
- 体内の基礎代謝が低下
- 肌ツヤが悪くなる
- ホルモンの分泌異常なども引き起こされる
といった症状が起こります。
しかし、
脂質は1gあたり9kcalと、たんぱく質や炭水化物に対して倍以上のエネルギーを生み出す
といった特徴があり、摂り過ぎると肥満や生活習慣病の原因にもなります。
余った脂質は、中性脂肪として体内に蓄えられますが、多く摂り過ぎれば肥満を招き、生活習慣病の原因となります。
引用元:厚生労働省 e-ヘルスネット|脂肪 / 脂質
そのため、ダイエットを行う上では脂質は摂り過ぎず、少なすぎず、適正範囲の摂取をすることが重要です。
摂りすぎにより消費しきれなかった脂質は中性脂肪へと変化し体脂肪として蓄えられますが、体脂肪には皮下脂肪と内臓脂肪があります。
- 皮下脂肪は体温を維持し、外部からの刺激を緩和
- 内臓脂肪は内臓を正常な位置に保ったり、エネルギーを蓄える役割
これらのバランスが崩れてしまい、内臓脂肪が増えすぎると糖尿病や高血圧などの生活習慣病の原因ともなります。
ダイエットを行う上では、脂肪を減らし過ぎないように気をつけながら余分な脂肪を減らすこともポイントです。
なお、エネルギー源を糖質から脂質へとシフトさせるケトジェニックダイエットという方法もありますが通常のダイエットの食事とはやり方が異なりますので注意が必要です。
C=Carbohydras/炭水化物は上手にコントロール

炭水化物は、わたしたちの体をつくるもとになる栄養素です。
炭水化物は
- 消化されて体のエネルギー源となる糖質
- 消化されずに糖の吸収を遅らせたり整腸作用がある食物繊維
の2つからできています。
炭水化物は1gあたり4kcalのエネルギーを生み出し、体の調子を整える役割
このエネルギーの中で食物繊維が生み出すのはわずか0〜2kcalであるため、そのほとんどが糖質からのカロリーです。
炭水化物には水を溜め込む性質もあるため、摂り過ぎると肥満の原因ともなります。
過剰な場合、エネルギーとして消費されなかった糖質は中性脂肪として蓄積され、肥満や生活習慣病の原因となります。
引用元:厚生労働省 e-ヘルスネット|炭水化物 / 糖質
さらに脂肪として貯蔵されるため、ダイエット時の摂取量には要注意です。
しかし不足すると脳のエネルギーが不足して集中力の低下やイライラなどが引き起こされます。
明確に摂取量は決まっておりませんが、厚生労働省が2020年に出した「日本人の食事摂取基準」によると1日に摂取するカロリーのうちの60〜65%を炭水化物にすることが推奨されています。
ダイエット中の食事で痩せる食べ物・おすすめ食材

ダイエット中に上手に取り入れたいおすすめの食べ物や食材をご紹介します。
どれか1つだけを食べるのではなく、これらの食材を上手く組み合わせ、満足感を得てリバウンドを防ぎましょう。
食物繊維、たんぱく質の含有量などを気にかけながら取り入れるとより効果的です。
肉類の痩せる食べ物・おすすめ食材
肉の部位でも、ひれ肉はロース部分の肉と比べて脂質が少ないためダイエット中にはおすすめの食材です。
また、牛肉の中でも最も脂が少ない部位はヒレ肉です。
バラ肉の場合は脂質が約50%も占めているのに対し、ヒレ肉は脂質が15%程度です。
肉の種類や部位によって含まれる栄養素も異なりますので、目的に合った部位を適量摂取しましょう。
鶏むね肉(皮なし)・ささみ
鶏肉は、たんぱく質を多く含みますが豚肉や牛肉と比べてカロリーが低いのでダイエットに向いています。
鶏肉は皮の部分に脂質を多く含むため、皮を取り除いた部分を食べるのがおすすめです。
さらに鶏むね肉とささみを比較すると、ささみの方が脂質が少ないためカロリーを抑えられます。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 鶏むね肉(皮なし) | 23g | 1.5g | 0g | 105kcal |
| ささみ | 22.5g | 0.8g | 0g | 98kcal |
脂の少ない牛・豚ヒレ肉
脂の少ない赤身の肉はダイエットに向いています。
ですが、鶏肉と比べると脂質が多くなり価格的にも牛肉や豚肉は高いためダイエットのために毎食食べることは困難なためたまのご褒美に取り入れるのが良いでしょう。
100g当たりの栄養素は下記の通りです。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 牛ヒレ肉 | 20.5g | 4.8g | 0.3g | 133kcal |
| 豚ヒレ肉 | 22g | 1.9g | 0.3g | 115kcal |
| 牛肉ランプ | 19g | 13.5g | 0g | 214kcal |
| 牛肉もも | 20g | 15.5g | 0.4g | 148kcal |
| 牛肉かた | 18.3g | 19.8g | 0g | 160kcal |
レバー
レバーは鉄分やビタミンA、ビタミンB12、葉酸などの栄養素を含んだ高タンパクな食材です。
鶏、豚、牛レバーの特徴を知り、運動後のたんぱく質の補給や疲労回復に上手に役立てましょう。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 鶏レバー | 18.9g | 3.1g | 0.6g | 100kcal |
| 豚レバー | 44.8g | 7.4g | 5.5g | 114kcal |
| 牛レバー | 19.6g | 3.7g | 3.7g | 119kcal |
豚レバーと鶏レバーには、皮膚を健康に保つビタミンAや体の機能や造血に係わるビタミンB12が多く含まれています。
100g当たりのカロリーは牛レバー(119kcal)>豚レバー(114kcal)>鶏レバー(100kcal)のため、選ぶなら鶏レバーがおすすめです。
魚類の痩せる食べ物・おすすめ食材
魚にはDHAやEPAなどの多価不飽和脂肪酸が多く含まれており、血液をサラサラにするだけでなく、脂肪の代謝を促進して体脂肪の燃焼を促す効果も期待できます。
刺身で生のままいただくと、栄養素が丸ごととれておいしいだけでなく、健康やダイエットにも最適です。
また魚も現在では、缶詰や瓶詰などの商品も豊富になり、より手軽に食べられるようになりました。
魚にも種類が多くありますが、特にダイエットにおすすめの食べ物をご紹介します。
魚の油は夜よりも朝に摂取したほうが吸収がよく、ダイエット効果も高まるとも言われていますので、ライフスタイルに合った魚を上手に取り入れてみてください。
赤身魚(マグロの赤身など)
マグロの赤身などの部分は、トロの部位と比べると脂分が1/3程度でカロリーも低く、良質なたんぱく質が多く含まれています。そのため、ヘルシーでダイエット食にも適しています。
さらに、ビタミンD、ビタミンB6、ビタミンB12、リン、セレンなどの栄養素や微量元素も含まれており、刺身でも加熱しても美味しく、レシピも豊富です。
中でもマグロは、加熱調理すると脂分が溶け出して旨味が増すメリットがあります。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| マグロの赤身 | 26.4g | 1.4g | 0.1g | 115kcal |
マグロやカツオなど常に泳ぎ続けている魚は、筋肉にミオグロビンという色素たんぱくを増やすことで酸素の運搬を効率よくしています。
ミオグロビンには鉄分が多く含まれているので、ダイエット中の鉄の補給にもおすすめです。
白身魚は鮭が優秀
鮭は身が赤いので赤身魚と思われがちですが、体側筋が白筋でできているため白身魚の一種です。
鮭は赤い色素であるアスタキサンチンを含むエビやカニなどの甲殻類をエサにしているため自身が赤くなります。
白身魚は、赤身魚や青魚よりも脂肪が少なく低カロリーなので、ダイエットに向いています。
中でも鮭が持つアスタキサンチンには、抗酸化作用があり、アンチエイジングや美肌、生活習慣病の予防などの嬉しい効果が期待できるのです。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 鮭の切り身 | 22.5g | 4.5g | 0.1g | 127kcal |
青魚は脂の量に要注意
ダイエットに向いているとされる青魚ですが、赤身魚・白身魚と比べると脂質が多く含まれており、カロリーが高めです。
しかし、青魚の油にはDHAやEPAなどの不飽和脂肪酸が豊富に含まれ、中性脂肪や悪玉コレステロールを下げるだけでなく、代謝を改善して脂肪の燃焼を促したり、脳血管障害や生活習慣病の予防・改善効果もあります。
サバやイワシ、アジ、サンマなど脂がのった魚は美味しく、ついつい食べ過ぎてしまいがちですが、いくら体にいい脂肪酸だからといって食べ過ぎには要注意です。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| サバ | 20.6g | 16.8g | 0.3g | 211kcal |
| イワシ | 19.2g | 9.2g | 0.2g | 156kcal |
| アジ | 19.7g | 4.5g | 0.1g | 112kcal |
| サンマ | 18.1g | 25.6g | 0.1g | 287kcal |
貝類
貝類は、糖質や脂質が低く、たんぱく質やビタミン類、亜鉛、鉄、マグネシウム、カルシウム、カリウムなどのミネラルも豊富なためダイエットに適した食材です。
アサリやホタテ、サザエ、シジミなど貝は種類も多く、レシピも調理方法もたくさんあります。
佃煮やチーズ焼きなど糖質や脂質の多い料理を避ければ、低カロリー・高たんぱくでダイエット食には強い味方です。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| アサリむき身 | 5.7g | 0.7g | 0.4g | 29kcal |
| ホタテ | 13.5g | 0.9g | 1.5g | 66kcal |
| サザエ | 19.4g | 0.4g | 0.8g | 83kcal |
| シジミ | 7.5g | 1.4g | 4.5g | 54kcal |
シーフード
シーフードのエビ、イカ、タコなどは食べ応えがありますが糖質や脂質が少なく低カロリーな食べ物です。
エビやカニには赤い色素であるアスタキサンチンが多く含まれています。
とくに殻付きのエビには100g当たり5.4mg(銀鮭100g当たり:0.97mg)と多くのアスタキサンチンがあり、抗酸化作用や疲労回復、美肌、がんや生活習慣病の予防などの効果が期待されます。
カロリーも鶏むね肉の半分ほどです。
また、イカやタコなどにはタウリンや亜鉛といった栄養素も含まれています。
タウリンはアミノ酸の一種ですが、血中のコレステロールの上昇を抑制したり、解毒作用を高める働きもあるのです。
さらに新陳代謝もアップさせてくれるため、老廃物が排泄されやすくなり、デトックス効果やダイエット効果も期待できます。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| エビ | 18.7g | 0.4g | 0.1g | 78kcal |
| イカ | 17.9g | 0.8g | 0.1g | 76kcal |
| タコ | 16.1g | 0.9g | 0.2g | 70kcal |
その他たんぱく質を摂れる痩せる食べ物・おすすめ食材
たんぱく質を効率よく摂れる食品は他にもあります。
卵、納豆、豆腐、おからなどは良質なたんぱく質を摂取できる貴重な食材です。
手に入りやすく、毎日の食生活に取り入れやすいため、不足しがちな栄養素や成分を補い、筋肉量を増やして基礎代謝を上げるためにうまく組み合わせて使いましょう。
卵
卵は、栄養価が高く、筋肉をつくり体の代謝を高める良質なたんぱく質を多く含むことからダイエットにとても適した食品です。
不飽和脂肪のリノール酸が多いため、悪玉コレステロールや中性脂肪を下げるだけでなく、脂肪を分解・消費してエネルギーに変える効果もあります。
ただし、食べ過ぎには要注意です。
1日1〜2個を目安に他の食材とのバランスをとりながら食事に取り入れることで、たんぱく質を補いながら効率的にダイエットができるでしょう。
| 60g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 卵1こ | 7.32g | 6.12g | 0.24g | 86kcal |
納豆
納豆は、炭水化物、脂質、たんぱく質の他、ビタミンやミネラル、食物繊維など多くの栄養素が総合的に含まれています。
また、大豆イソフラボンというポリフェノールは、女性ホルモンに構造が似ており、更年期や骨粗鬆症の予防にも効果的に作用します。
この他、大豆サポニンには強力な抗酸化作用があり、脂肪の酸化を抑制しつつ脂肪燃焼を促進するためダイエットにも非常に適した食材です。
大豆たんぱくは肉とほとんど同じ働きですが、肉よりも低カロリーでヘルシーです。
ただし、納豆はビタミンKを多く含むため、ワーファリンなどの抗凝薬を服用している方は注意してください。
| 50g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 納豆1パック | 8.25g | 5g | 6.05g | 92kcal |
豆腐
豆腐には、たんぱく質のほか、マグネシウム、鉄、カルシウム、食物繊維、ビタミンB群などさまざまな栄養素が含まれています。
低カロリーで一丁で食べ応えがあるため、ダイエット食材としてとても人気があります。
絹ごし豆腐と木綿豆腐では、木綿豆腐の方がややカロリーがありますが、料理やトッピングに合わせて使い分けるとよいでしょう。
サラダのトッピングとしてトマトやシラス、ネギなどを一緒に摂るのもおすすめです。
ただし、冷奴は体を冷やすため、夜や冬場などは湯豆腐などにして食べるとさらに美味しくいただけます。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 豆腐 | 5.3g | 3.5g | 2g | 56kcal |
おから
おからは質のよいたんぱく質や食物繊維が含まれており、食物繊維が大腸まで届くため腸内環境の改善にも役立ちます。
上手に料理に使用すると、低カロリーでたんぱく質が摂取できるだけでなく、腸内環境が整うことで便秘や代謝も改善されてダイエットの手助けをしてくれるでしょう。
摂取目安は生のおからで1日に30〜40g、乾燥おから(おからパウダー)で15gです。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 生おから | 6.1g | 3.6g | 13.8g | 88kcal |
| 乾燥おから | 23.1g | 13.6g | 52.3g | 333kcal |
乳製品の痩せる食べ物・おすすめ食材
乳製品には脂肪分が多く含まれているため、そればかりを多く食べてはダイエットに逆効果です。
しかし、乳製品には脂肪だけでなく、ビタミンやカルシウム、マグネシウム、リン、亜鉛などの栄養素も多く含まれています。
そのため、摂り過ぎないようにカロリー制限をしながら、ほかの食材と一緒に摂取することで満腹感を増幅させ、栄養面でも体重コントロールの面でもダイエットの手助けをしてくれるのです。
プロセスチーズ・カッテージチーズ
チーズは乳由来の良質なたんぱく質が豊富に含まれています。
そのため、筋肉を増やし、基礎代謝を向上させることで脂肪を燃焼しやすくする効果が期待されます。
ダイエット中にチーズは厳禁だと思われがちですが、チーズの脂肪には短鎖脂肪酸と中鎖脂肪酸が含まれており、短鎖脂肪酸は脂肪と結合して脂肪を燃焼させる効果があります。
また、中鎖脂肪酸は普通の脂肪よりも早く分解されるため、体内に蓄積されにくいという特徴があるのです。
塩分量やカロリー、脂肪などに注意すれば、ダイエットに適したチーズもあります。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| プロセスチーズ | 22.7g | 26g | 1.3g | 313kcal |
| カッテージチーズ | 13.3g | 4.5g | 1.9g | 99kcal |
ヨーグルト(無糖)
ヨーグルトにはカルシウムやカリウムなどのミネラルやビタミンだけでなく、たんぱく質も含まれています。
ダイエット中は、筋肉量を落とさないように適度なたんぱく質を摂取することが大切です。
睡眠中に成長ホルモンが分泌されて筋肉がつくられるタイミングに合わせて寝る前に摂取するのもいいでしょう。
乳酸菌は酸に弱いため、食前よりも食後の酸が弱まったタイミングで食べるほうがより効果的です。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| ヨーグルト(無糖) | 3.6g | 3g | 4.9g | 56kcal |
海藻類の痩せる食べ物・おすすめ食材
海藻類は、低カロリーでミネラルも多くダイエットにも人気の食材です。
よく噛んで食べることで満腹感も増し、食物繊維の効果で整腸作用や血糖上昇抑制作用、代謝促進なども期待されています。
また、海藻類にはフコキサンチンというカロテノイドが含まれており、近年は抗肥満作用、抗酸化作用、抗がん作用、血管新生抑制作用なども注目されている食べ物です。
わかめ
わかめは食物繊維が多く、食べると満腹感も出やすいことから食事の最初に食べると食べ過ぎを予防できます。
また、食物繊維の中でも水溶性食物繊維が豊富なため、腸の中で発酵して腸内細菌のエサとなり整腸作用もあります。
腸が整い便秘が解消されて法廃物が排泄されると、代謝もアップするでしょう。
さらに血糖値の上昇も抑制するため、インスリンの過剰分泌を抑え、脂肪が蓄積されるのも防ぎます。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| わかめ | 1.9g | 0.2g | 5.6g | 24kcal |
もずく・めかぶ
もずくやめかぶはヌルッとした粘りのある海藻です。
もずくやめかぶに含まれるヨードは基礎代謝を促進し、新陳代謝を活発にする働きもあります。
フコキサンチンというカロテノイドが脂肪を熱に変えるため、脂肪細胞が小さくなるとして注目されています。
もずくとめかぶを栄養素で比較すると、めかぶの方が全体的にカロリーや栄養価が高く、もずくの方がより低カロリーでダイエット向けと言えます。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| もずく | 0.2g | 0.1g | 1.4g | 4kcal |
| めかぶ | 0.9g | 0.6g | 3.4g | 14kcal |
昆布
アルギン酸とフコダインという水溶性食物繊維を含み、免疫力の向上や生活習慣病の予防などの効果も期待されています。
昆布には鉄分も含まれているため、貧血予防だけでなく顔色を良く見せる美容効果もあるのです。
昆布の中でも細目昆布に最も多く鉄分が含まれています。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 昆布 | 8.3g | 1.5g | 58.5g | 205kcal |
ひじき
ひじきは、ビタミン、ミネラル、鉄、食物繊維などの栄養素が多く含まれています。
食物繊維で腸内環境が整うと便秘が解消されるだけでなく基礎代謝や免疫力も上がります。
また、ビタミンB2には糖質や脂質の代謝を促す効果もあり、美容やダイエットに効果のある食べ物です。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| ひじき | 10.6g | 1.3g | 56.2g | 139kcal |
こんにゃく
こんにゃくはこんにゃく芋からできており、約97%が水分です。
カロリーや糖質、たんぱく質がほとんどなく、グルコマンナンという食物繊維が主成分です。
グルコマンナンは人間が分解・消化することができないため、そのまま腸に行き、排便を促したり、コレステロールを吸着し出す働きをします。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| こんにゃく | 0.1g | 0.1g | 3.3g | 8kcal |
ところてん
ところてんの主な栄養素は食物繊維です。
ところてんには水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の2種類が含まれており、食後の血糖上昇やコレステロールの低下作用、生活習慣病の予防などの効果が期待されています。
低カロリーで食物繊維が豊富なヘルシーフードです。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| ところてん | 0.2g | 0g | 0.6g | 2kcal |
野菜の痩せる食べ物・おすすめ食材
野菜にはビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富に含まれており、ダイエットには欠かせない食材です。
野菜ごとに含まれる栄養素が異なるため、必要な栄養素を補給できる野菜を毎日上手に使いましょう。
ブロッコリー
ブロッコリーにはビタミンC、ビタミンB群、葉酸、鉄、カルシウム、食物繊維、βカロテンなど多くの栄養素が含まれています。
さらに他の野菜と比べて糖質が少なく、たんぱく質が多めです。
効率的にたんぱく質や栄養素を摂りつつ、ダイエットを続けたい方にはとてもおすすめです。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| ブロッコリー | 5.4g | 0.6g | 6.6g | 37kcal |
オクラ
オクラは、ビタミン、ミネラル、食物繊維などに加えて、ペクチンというねばねばした水溶性食物繊維が含まれています。
ペクチンは、胃粘膜保護作用や整腸作用、免疫力の向上効果などもあり、コレステロールの低下にも役立ちます。茹ですぎると栄養素を損ないやすい食材なので、電子レンジを活用するとよいでしょう。
オクラ100g当たりの栄養素は、脂質:0.2g、たんぱく質:2g、炭水化物:6g。
アスパラガス
アスパラガスは、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンE、ビタミンB1、B2、葉酸などに加え、アスパラギン酸の新陳代謝促進効果や疲労回復効果などがあります。
また、ルチン、アルギニンには動脈硬化の予防効果や貧血予防なども期待されており、栄養価が高く低カロリーの緑黄色野菜です。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| アスパラガス | 2.6g | 0.2g | 3.9g | 21kcal |
小松菜
小松菜は、鉄やビタミンC、カルシウム、カロテンなどが豊富に含まれています。
中でもカルシウムはほうれん草の3倍以上で、牛乳に匹敵します。
下処理なしで料理にも使いやすく、年間通して安価で手に入るため、栄養補給や疲労回復にぴったりの食材です。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 小松菜 | 1.5g | 0.2g | 2.4g | 13kcal |
ほうれん草
ほうれん草は、βカロテン、ビタミンA、ビタミンC、鉄、葉酸、カリウムなどが含まれています。
βカロテンは抗酸化作用があるため、がんの予防のほか美肌効果やアンチエイジング効果もあります。
さらに、カリウムは体内に蓄積された塩分を排泄し、むくみや高血圧にも役立ちます。
冬場に採れたほうれん草は、夏のものよりもビタミンCを多く含むため、とくに冬のほうれん草はおすすめです。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| ほうれん草 | 2.2g | 0.4g | 3.1g | 18kcal |
キャベツ
キャベツには、ビタミンUという胃酸分泌抑制作用、胃腸粘膜の修復作用があるビタミンが含まれています。
胃腸薬のキャベジンとしても有名ですが、ビタミンUは水溶性で熱にも弱いため、生で食べることをおすすめします。
キャベツにはほかにもビタミンCやビタミンB、葉酸やカルシウムなど多くの栄養素があり、ビタミンCはキャベツ3枚で成人1日分の必要量を補えます。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 1.2g | 0.1g | 5.2g | 23kcal |
ピーマン
ピーマンはビタミンAとビタミンCを豊富に含み、栄養価が高い野菜です。
さらに100gあたり2.3gもの食物繊維が含まれているため、ダイエットの敵である便秘にも効果的に作用します。
糖や脂肪を排泄する作用もあるため、肥満防止や生活習慣病の予防にも効果的です。
ピーマンは、種もわたもヘタも栄養がある可食部ですので、栄養を損なわないために傷つけず、丸ごと食べるのがおすすめです。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| ピーマン | 0.9g | 0.2g | 5.1g | 20kcal |
キノコ類の痩せる食べ物・おすすめ食材
キノコはカロリーが低い上に、食物繊維をたっぷり含むためダイエットにはとてもいい食べ物です。
キノコの種類によっても異なりますが、ビタミンB1、B2やビタミンD、カリウム、リンなどが含まれています。
カリウムには体内の余分なナトリウムを体外へ排出する作用があるため、むくみも解消されるでしょう。
キノコの約90%が水分であるため、残りの多くが食物繊維です。
またキノコには、キノコキトサンという高分子のキトサンが含まれており、体脂肪減少効果や脂肪吸収抑制効果が示されています。
きのこ全般OK
キノコにはしめじ、まいたけ、しいたけ、エリンギ、ぶなしめじ、なめこ、マッシュルームなど多くの種類がありますが、キノコキトサンはとくにえのきたけに多く含まれています。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| えのきたけ | 2.7g | 0.2g | 7.6g | 34kcal |
糖質の痩せる食べ物・おすすめ食材
ダイエットでは糖質を減らすことが大切です。
それは、糖質を減らすことで血糖値の上昇を穏やかにすることができ、インスリンの分泌を抑え脂肪が蓄えられるのを防ぐためです。
もう一つの理由は、エネルギーとして脂質よりも糖質が優先的に使われるからです。
そのため、脂質を減らすためには糖質を少なくすることが結果的に痩せることにつながります。
玄米・押し麦・もち麦
押し麦ともち麦はどちらも大麦からできているため、栄養成分に大差はありません。
どちらもビタミン、ミネラル、食物繊維などを豊富に含んでいます。
食物繊維の中のβグルテンは、糖質や血糖値の上昇を抑制するため、健康的に痩せたい人には向いてる食材です。
また、玄米はGI値という糖の吸収を示す値が低いため、糖が脂肪になりにくいという特徴も持っています。
これらの食材は単独で使っても、好みで混ぜてもダイエットに適しています。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 玄米 | 2.8g | 2.8g | 35.6g | 152kcal |
| 押し麦 | 6.7g | 1.5g | 78.3g | 329kcal |
| もち麦 | 9.5g | 2.1g | 65.2g | 339kcal |
十割そば
そば粉は小麦粉よりも炭水化物と糖質が少ない食材です。
そのため、そばの中でも小麦粉を含まない十割そばが最もダイエットに適しています。
そばにはたんぱく質やビタミン、アミノ酸、ルチンなどの栄養素が豊富に含まれているほか、食物繊維も多くGI値が低いという特徴があります。
そのため、糖を脂肪として溜め込ににくい性質があり、うどんや白米よりも痩せやすい食べ物です。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 十割そば | 8.7g | 1.5g | 77.1g | 356kcal |
オートミール・キヌア
オートミールとは、オーツ麦を脱穀して食べやすくしたものです。
栄養価が高く、カルシウムは玄米の約5倍、食物繊維は玄米の約3倍も含まれています。
また、たんぱく質やミネラルも豊富なので、ダイエット中の人の栄養補給にも向いています。
たんぱく質や食物繊維はキヌアよりもオートミールの方が優れていますが、オートミールよりもキヌアの方がカリウムやマグネシウムなどのミネラルに優れています。
また、キヌアはグルテンフリーなのでカロリーも抑えられます。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| オートミール | 13.7g | 5.7g | 69.1g | 350kcal |
| キヌア | 12.7g | 6g | 64.9g | 343kcal |
干し芋・さつまいも
脂肪燃焼効果のあるビタミンB群はさつまいもに豊富に含まれています。
さらに乾燥させることで倍近く増えます。
糖質やカロリーが高いため食べ過ぎには注意が必要ですが、食物繊維やビタミン、カリウムなどが摂取できるためダイエット中のおやつなどに最適です。
| 100g当たり | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 干し芋 | 3.1g | 0.6g | 71.9g | 277kcal |
| さつまいも | 1.2g | 0.2g | 31.9g | 126kcal |
ダイエット中でもOKな調味料とは?
ダイエット中の食事は、糖分や塩分、脂質をなるべく控えたいものです。
そのため、塩はもちろん、糖分を多く含むみりん、焼肉のたれ、はちみつ、ケチャップ、ソース、脂質の多いごまだれやマヨネーズなどはできるだけ避けましょう。
おすすめの調味料は酢やレモン汁、だし汁などです。
酢は抗酸化作用に加えて脂肪燃焼効果もあるため、積極的に使いたい一品です。
ぽん酢もカロリーや塩分が控えめでおすすめです。
しかし、摂り過ぎると胃に負担がかかるので1日15mlが目安です。
食事の際は醤油やソースの代わりに、ハーブやレモン汁、ゆず胡椒などを上手に使うと物足りなさを解消できるでしょう。
どうしてもドレッシングを使いたいときは、ノンオイルでカロリーオフのものを選びましょう。
醤油や味噌も減塩のものを選んで使うとOKです。
にんにく、しょうが、カレー粉などを組み合わせると味に変化がつくだけでなく、体温が上がり代謝も向上します。
参考:カロリーSlism|日本食品標準成分表2020年版(八訂)
ダイエット成功のための痩せる食事方法12選
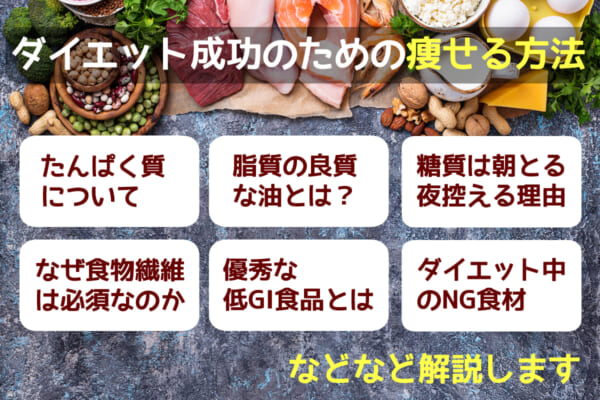
ダイエットを成功させるためには、正しい食事方法と必要な栄養素を知ることが大切です。
- 痩せるために必要なのはどの栄養素なのか
- 減らすべき成分は何なのか
- 食べる量や食べ方
などの痩せるための食事方法を伝授いたします。
ダイエット中は脂質を減らしたんぱく質を増やす
脂質はカロリーが高いため、ダイエット中はなるべく脂質を減らした食べ物を選びましょう。
1日の脂質の摂取量は総カロリーの20%以下に抑えるようにしてください。
逆に、たんぱく質を減らしてしまうと筋肉量も低下してしまいます。
筋肉が少ないと基礎代謝が上がらないため痩せにくい体になります
ダイエットの食事では、脂質を減らしたんぱく質を増やしましょう。
ダイエット中に摂りたいたんぱく質の量は、体重1kgに対して1gですので50kgの女性なら50gの摂取がおすすめです。
痩せる食事に必須!ダイエット向きのたんぱく質とは?
痩せる食事におすすめのたんぱく質は、
- 脂身の少ない赤身の肉
- サラダチキン
- 魚
- 野菜
- 豆腐
などです。
たんぱく質には動物性と植物性がありますが、どちらもバランスよくダイエット中の食事で摂りましょう。
動物性のたんぱく質で必須アミノ酸を補い、植物性たんぱく質ではミネラルやビタミン、食物繊維などを補ってください。
ダイエット向きのたんぱく質は、低カロリーなものを選ぶことがポイントです。
| OK/NG | 肉 | 魚 | 野菜 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| OK食材 | ササミ、むね(皮なし) | 赤身魚、白身魚、青魚 | 全般OK | キノコ類や海藻 豆腐、穀類 |
| NG食材 | ロース、バラ、脂身 | トロの部分 | 根菜や芋類の 摂り過ぎ注意 | 揚げ物、ジャンクフード 加工食品 |
足りない分はプロテインで補い筋肉量を維持する
食事からのたんぱく質が不足しがちなときは、プロテインで補いましょう。
プロテインを効率的に摂取することで筋肉量を維持しやすくなります。
また、プロテインは満腹感をもたらしてくれるため、間食などのカロリーがカットできるのも利点です。
たんぱく質は筋肉だけでなく、髪の毛や臓器の形成、ホルモンや抗体など体の健康維持に欠かせない栄養素です。
不足すると筋肉の低下だけでなく体調を崩す原因にもなるためしっかり補いましょう。
脂質は「質」を重視!良質な油を選ぶようにする
脂質を作っている脂肪酸は、構造の違いから「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」に分けられます。
脂肪酸は、炭素、酸素、水素で構成されていますが、
- 炭素同士の二重結合を全く含まないものを飽和脂肪酸
- 炭素=炭素の二重結合を含むものを不飽和脂肪酸
といった違いがあります。
不飽和脂肪酸の中でも、炭素に結合する水素の位置でシス型とトランス型に分類されます。
トランス型不飽和脂肪酸は人工的に生成されることが多く、体にとって悪い影響を与えることもあるため食事で摂り過ぎないように注意が必要です。
脂質を摂る際には、動物性を控え、植物性を積極的に摂取するなど良質な脂を選びましょう。
飽和脂肪酸は控えめに
飽和脂肪酸とは、
- 肉
- バター
- ココナッツオイル
などに含まれる動物性の脂肪酸です。
飽和脂肪酸の脂は常温で固体になるほど融点が高く、多く摂り過ぎると血液がドロドロとなり、血液中のLDL(悪玉)コレステロールを上昇させ、中性脂肪を増加させます。
その結果、動脈硬化や冠動脈疾患、生活習慣病の悪化などを招く要因となります。
飽和脂肪酸の脂質は、肥満を助長してダイエットを邪魔するだけでなく、健康被害ももたらす
また、不飽和脂肪酸は体内で合成できないため食事から摂取する必要がありますが、飽和脂肪酸は体内合成ができる脂肪です。
そのため、食事からの摂取を控えても問題ありません。
体内の代謝も落さず、血液や血管も健康を保つためにはなるべく飽和脂肪酸の摂取を控えるように心がけましょう。
飽和脂肪酸は、1日の総カロリーの7%以下になるように抑えることが推奨されています。
不飽和脂肪酸は積極的に
不飽和脂肪酸は常温で液体の低い融点で、植物性の食品や魚に多く含まれる脂肪酸です。
体内で合成できないため、食事から摂取する必要がある必須脂肪酸です。
不飽和脂肪酸も、炭素の二重結合の数によってさらに一価不飽和脂肪(n-9系脂肪酸)と多価不飽和脂肪(n-6系脂肪酸、n-3系脂肪酸)に分類されます。
アーモンドやオリーブ油などに多く含まれています。
リノール酸は大豆油やコーン油などの植物油に多く含まれ、適量を摂取することで中性脂肪や悪玉コレステロールを減らす効果も示されています。
青魚や亜麻仁油、えごま油などに多く含まれ、体内で代謝されてDHAやEPAとなるものです。
DHAやEPAは中性脂肪や悪玉コレステロールを下げるだけでなく、脳の活性化や免疫機能の向上、美肌、生活習慣病の予防など多くの効能がありダイエットや健康増進に効果があります。
飽和脂肪酸よりも不飽和脂肪酸を積極的に摂取するべきですが、脂肪は他の栄養素と比べて1gあたり9kcalもカロリーがあるため摂り過ぎには要注意です。
トランス脂肪は避けるが吉
トランス脂肪酸は、
- マーガリン
- ショートニング
- 業務用の揚げ油
- 菓子パン
などに含まれる脂肪酸です。
血液中の善玉コレステロールを減らし、悪玉コレステロールを増やすため動脈硬化や心疾患などの冠動脈疾患のリスクを高めることが懸念されます。
WHO/FAO合同専門家会議では、トランス脂肪酸の摂取を一日の摂取エネルギーの1%以下にするように示しています。
飽和脂肪酸よりもトランス脂肪酸の方がコレステロールを上昇させると言われているため、なるべくダイエット中の食事に限らず避けるのが吉でしょう。
参考:消費者庁|トランス脂肪酸の表示に向けた今後の取組について
糖質は朝にしっかりと摂り、夜は控える
ダイエットで糖質を抑えたいからと言っても、毎食糖質を制限するのはストレスもたまり大変です。
そこで、1日の活動を開始する朝はしっかりと摂りましょう。
糖質が少ないと、体はたんぱく質をエネルギー源として使ってしまうので筋肉量が低下してしまう可能性があります。
日中の運動量に見合った糖質であれば、朝の食事でしっかりとってもかまいません。
逆に夜は運動量が少ないため控えめにしましょう。
ダイエットに必須!食物繊維で腸内環境を整える
痩せるカギは食物繊維が握っていると言っていいほど、ダイエット中の食事に食物繊維は必須です。
食物繊維には、血糖上昇抑制作用、脂質・糖質の排泄作用など多くの働きがありますが、中でもダイエットを成功へと導いてくれる働きは整腸作用です。
ですが現在、多くの日本人が食物繊維の摂取量が不足気味と言われています。
厚生労働省策定の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、一日あたりの「目標量」(生活習慣病の発症予防を目的として、現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量)は、18~64歳で男性21g以上、女性18g以上となっています
引用元:厚生労働省 e-ヘルスネット|食物繊維の必要性と健康
腸内環境は善玉菌と悪玉菌の多さによって決まりますが、悪玉菌が多いと栄養素を必要以上に吸収して太りやすくなるほか、便秘がちになり基礎代謝も悪くなります。
食物繊維は消化も吸収もされないため、そのまま小腸を通過して大腸へ入ります。
すると、大腸の中で善玉菌のエサとなり善玉菌を増やし、腸内環境を整える作用があるのです。
腸内環境が整うと、便秘が改善されるほか、基礎代謝が高くなり、脂肪も燃焼しやすくなります。
便のかさを増す不溶性食物繊維
食物繊維には2種類あり、水に溶けないものを不溶性食物繊維と言います。
不溶性食物繊維は保水性に優れているため、胃や腸で膨らみ、腸壁を刺激したり、便のかさを増す作用があります。
また、体内の有害物質を吸着して一緒に排泄されるので、発がん物質の除去効果も期待されています。
不溶性食物繊維が大腸に入ると、分解・発酵されて善玉菌であるビフィズス菌を増やし腸内環境を整えることで整腸効果を担っているのです。
しかし、食事で摂り過ぎると便の量が多くなり過ぎて逆に便秘になることがあるため要注意です。
キノコ類、穀類、豆類、ゴボウ・レンコン・トウモロコシなどの野菜に含まれます。
便を柔らかくする水溶性食物繊維
一方、水に溶けるものを水溶性食物繊維と言います。
水溶性食物繊維は水に溶けて胃腸のなかをゆっくりと動くため、ゼリー状となった食物繊維が糖の吸収速度を穏やかにしてくれます。
インスリンは糖を脂肪として溜め込む性質がありますが、水溶性食物繊維の働きで食後の血糖上昇が穏やかになるとインスリンの過剰分泌も防ぐことができます。
また、水溶性食物繊維は便と一緒にコレステロールを排出する効果もあるため、血中コレステロール濃度低下も期待されています。
不溶性食物繊維と同じく、大腸ではビフィズス菌を増やして腸内環境を整えます。
過剰摂取により、便が水状となり下痢になることがあるため注意してください。
海藻類、果物類、麦、にんじん、だいこんなどに多く含まれます。
血糖値の上昇を抑える低GI食品を知っておく
GI値とは、Glycemic Indexの頭文字をとったもので、糖の吸収度合いを示す数値です。
食事の後、糖が吸収される程度によってインスリンが分泌されますが、インスリンには血糖を下げる働きだけでなく、糖を脂肪に変える働きもあるのです。
そのため、食後の血糖値の上昇をなるべく穏やかにすることがインスリンの分泌を抑え、ダイエットに繋がるのです。
GI値の低い食べ物は、
- 葉物野菜
- キノコ類
- ブロッコリー
- ピーマン
- 穀物
などです。
食事を食べる順番も、まずは葉物野菜を食べ、その後おかず、主食などを食べ進めるとよいでしょう。
夜ご飯は18時までに食べるのが理想!遅くても21時まで
夕食を18時までに終えるのが理想的な理由には、就寝前までに食べ物を消化して内臓を休ませる目的があります。
遅くても21時までには食事を食べ終えましょう。
就寝時間の3〜4時間前までには食べ終えるのが理想です。
夜は内臓も休憩モードとなるため、遅い時間に食事をすると血糖値が上がりやすくなり、肥満や高血糖の原因となってしまいます。
体内時計を整え、規則正しい食生活を送りましょう。
1日に摂る水分は2リットルが理想的
ダイエット中に摂る水分量は2リットルを目安にしましょう。
2リットルの水を飲むと、細胞の隅々まで水分が行き渡り、細胞が活性化して代謝が上がります。
また、血液の流れがよくなり、脂肪が燃焼しやすくなるとも言われています。
水分を摂ることで老廃物が出やすくなるので、巡りがよくなりデトックス効果も期待されます。
カロリーが0であれば、水以外にも麦茶や炭酸水でもOKです。
なお、カフェインを多く含むコーヒーや緑茶、紅茶といった飲み物は利尿作用により不要でない水分までも排出してしまうためダイエット中の水分には不向きとなります。
アルコールは控えめに!飲むなら糖質0の蒸留酒
アルコールは、満腹中枢を刺激して食欲を増進させる働きがあります。
ダイエット中に飲むことで、食事やおつまみを食べ過ぎてしまう要因にもなるため控えましょう。
さらにアルコールは腸内環境も悪化させてしまいます。
腸内環境が乱れると、便秘や肥満のもとになるため注意が必要です。
ビールや日本酒、ワインなどの醸造酒は糖質が高いのに比べて、蒸留酒は糖質が0のものがあります。
ダイエット中は余分なカロリーは避けるべきですが、糖質0の蒸留酒をシロップや果汁などで割らずに水割りやロックで飲むならOKです。
ダイエット中にNGな食事・控えたほうがいいものを知っておく
現在はコンビニやスーパーが多くあり、食事のハードルも低くなりました。
しかし、コンビニ弁当や加工食品はダイエット中には要注意です。
ハムやソーセージなどは手軽で食べやすいですが、塩分が多めでむくみやすくなります。
また、揚げ物などのジャンクフードも糖質や脂質の塊なので控えましょう。
なお、ダイエットをする際は食品の裏に記載されている栄養成分表示を見るクセを付けておくとエネルギー以外にも、たんぱく質や脂質、炭水化物の量を把握することが可能です。
参考:消費者庁|栄養成分表示を活用して、バランスのよい食事を心がけましょう!
ダイエットレシピは料理のレシピサイトを活用する
ダイエット中でも食事や料理は楽しみたいものです。
そこで、ダイエットレシピに特化したサイトを活用してみてはいかがでしょうか。
自分のレパートリーにはなかった料理や簡単でヘルシーなアイデアがたくさん掲載されています。
鶏団子とキャベツのスープなど、栄養素も逃がさずに、体も温まりやすい簡単な料理が満載です。
他にも「ダイエット レシピ」で検索するとたくさん見つかるため、是非参考にしてみてください。
ダイエット中の食事記録はアプリを利用!PFCバランスも自動で計算できるおすすめアプリ2選

ダイエット中の食事の記録やカロリー計算、PFCバランスへの配慮など全部自分で行うのはとても大変です。
しかし、今は簡単に使えるアプリがあります。
自動で計算してくれるので、毎日の記録も負担になりません。
おすすめの2つのアプリをご紹介しますので、使いやすいものを選んでください。
初心者でも続けやすい「あすけん」
あすけんは、ダイエットの食事はもちろん健康もサポートしてくれるアプリです。
栄養士からのアドバイスが20万パターン以上あり、自分に最適のアドバイスをもらえるだけでなく、簡単に食事の記録ができます。
食事の写真や食品のバーコードを撮るだけで記録でき、次の食事のアドバイスがもらえます。
無料コースと有料コースがありますが、まずは7日間の無料お試し期間があるため自分にあったプランが選べます。
食べないダイエットより、食べるダイエット。あすけんに食事を記録して健康的な食生活へ
引用元:あすけんダイエット
シンプルで使いやすい「MyFitnessPal」(マイフィットネスパル)
マイフィットネスパルは、食事の内容だけでなく、栄養、運動、体重も記録できる世界でも人気のアプリです。
自分の目標に合わせてPFCの設定もでき、食品データに基づいた食事の登録が簡単にできます。
また、コミュニティにも参加できるため、情報を共有しつつダイエットを継続できるのも魅力です。
無料で使用できる範囲が広く、データベースの多さには圧巻です。
マイフィットネスパルにも有料版があり、記録データをファイルとして保存することができます。
健康は食べるものから始まります。もっと食事に気を付けて「マインドフル」な食生活を心掛けませんか?
引用元:MyFitnessPal
ダイエット中の食事についてのよくある質問
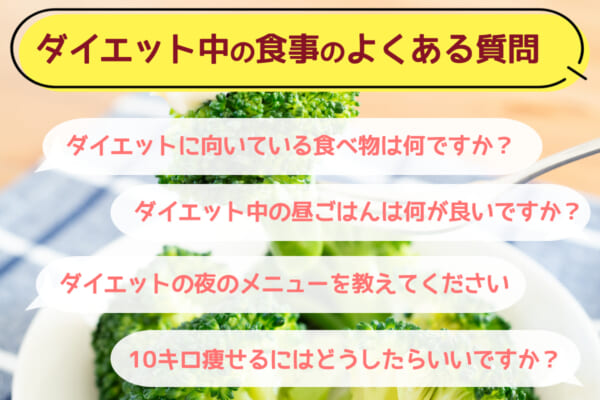
ダイエット中の食事についてよくある疑問や質問をまとめました。
間違ったダイエット方法を進めると、かえって太りやすくなったり、リバウンドをすることにもなりかねません。
正しい知識と方法で、適切な食べ物を適量食べることが大切です。
ダイエットに向いている食材、食べ方、食べるタイミングなどをもう一度確認してから実践しましょう。
ダイエットに向いている食べ物は何ですか?
ダイエットには、低カロリーで高たんぱく、食物繊維の多い肉・卵・大豆・野菜類などの食材が向いています。
ダイエットの食事における摂取カロリーは、自身の消費カロリーを超えないことが原則なのでカロリーを抑える必要がありますが、必要な栄養素はしっかり摂らないといけません。
たんぱく質が少ないと筋肉量が低下してしまい、基礎代謝が下がって痩せません。
また、不飽和脂肪酸に含まれる良質な脂はダイエットに効果的に働くため、魚介類やアーモンドなどの種実類なども食事に上手く取り入れましょう。
ダイエットの食事で昼ごはんは何が良いですか?
ダイエット中の昼ごはんは、食物繊維や炭水化物、たんぱく質が多く含まれているものを摂りましょう。
脂質、糖質は控えるほうがベストです。
昼食におけるエネルギーは、1日の総カロリーの約40%を目安に考えるとよいでしょう。
体を温めて基礎代謝を上げるために、具たっぷりのスープなどの食事メニューもおすすめです。
パスタもソースだけではなく、パスタサラダなどにして栄養バランスを整えましょう。
ダイエットの食事で夜のメニューを教えてください
ダイエット中の夕食は、多めの食物繊維、高たんぱく、低脂質のメニューを意識しましょう。
豆腐や野菜、ささみ肉などをつかったスープや鍋、納豆やアボカド、卵入りの丼などもおすすめです。
塩分が多いとむくみの原因になるため、味付けは薄めの食事を心がけるのがポイントです。
10キロ痩せるにはどうしたらいいですか?
健康的に10キロ痩せるためには、急激なダイエットは避け、正しい方法で栄養の過不足なく減量することが大切です。
そのためには、一か月で体重の5%以上の減量は控えましょう。
食事を摂らないなどの極端な偏食は避け、PFCを意識したバランスのよい食事を心がけましょう。
また、摂取カロリーが消費カロリーを上回らないように計算し、基礎代謝を上げるため筋肉量が落ちないように適度な運動や筋トレを取り入れてください。
10キロ痩せるためには約72,000kcalの消費が必要です。
日々の摂取カロリーが消費カロリーの約90%程度になることをおすすめします。
ダイエット中の食事:まとめ
ダイエット中の食事は、良質なたんぱく質を不足なく摂取して筋肉量を落さずに基礎代謝を上げることが大切です。
そのためには、偏った栄養バランスをなくし、全体的にバランスのとれた食事をすることが重要です。
極端なカロリー制限や、偏食はかえって基礎代謝を下げるだけでなく、その後のリバウンドにも繋がるため避けてください。
ダイエット中のカロリー摂取の原則は、消費カロリー>摂取カロリーとなることです。
毎日200〜240kcalずつ無理なく減らしていくことで、ストレスを最小限に抑えて減量することができます。
正しいカロリー摂取法と栄養素の知識を持って、ダイエットの食事を楽しむ余裕ができるとより快適に日々を過ごせるようになるでしょう。
どうしても食べてしまう、食欲が抑えられないといった際はGLP-1ダイエットもおすすめです。
1日1錠飲むだけのリベルサスを使用すれば、自然に食欲を抑制することが可能です